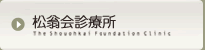インプラントの歴史
古来からおこなわれてきたインプラント

失った歯を人工材料で補う試みは古くから行われてきました。上顎骨に鉄製のインプラントが埋まった紀元2世紀から3世紀の古代ローマ時代の人骨が発見されており、このことはすでにインプラント治療が試みられていたことを示しています。
7世紀のマヤ文明の遺跡で発掘された 20歳代女性の下顎骨に天然の抜去歯2本と貝でできたインプラントが埋まっており、歯石がついている事、周囲に骨造成がエックス線検査で確認できる事からかなり長期に機能した事を示しており世界で最初の実用 に耐えたインプラントだと考えられています。
インプラントが臨床に登場したのは1910年代。1913年にグリーンフィールドが円筒型のインプラントを開発し、これが近代インプラントの祖と評される事が多いです。
1930年代にはスクリュー 型、1940年代にはらせん型のインプラントが考案されました。しかし予後は著しく悪かったのです。インプラント治療最大のブレークスルーと言われるのが 1952年スウェーデンのルンド大学で研究を行っていたペル・イングヴァール・ブローネマルク教授によって、チタンが骨と結合すること(オッセオインテグレーション)が発見され、チタンがインプラントに応用されるようになった事です。これによりしっかりと骨に結合するインプラント治療が可能になりました。動物実験を経て、1962年から人間に本格的にインプラント治療が行われるようになりました。ただ、ブローネマルク教授が歯科医師ではなかった事などがあり、批判的な立場の歯科医師も多く普及には至りませんでした。
1978年に初のデンタルインプラントのコンセンサス会議が、ハーバード大学とアメリカ国立衛生研究所の共催で開催されました。この会議はデンタルインプラントのデータ収集と分析の評価基準と標準が確立された象徴的な会議であったと評価されています。大きな ターニングポイントとなったのは1982年のトロント会議。そこで予後15年の症例が報告され、一大センセーショナルを巻き起こし、北米を中心に普及が始まりました。
インプラントの形態は大きく分けてブレードタイプと呼ばれる板状のものとルートフォームと呼ばれる歯根様のタイプがあるがルートフォームが主流になり現在に至ります。ルートフォームは当初はシリンダータイプと呼ばれる滑らかな表面でしたが、ネジ状の形態の方が初期固定に有利とわかり、現在のインプラントにはネジ山(スレッド)がつくタイプになっています。 さらに骨との結合を早期かつ強固にするため、フィクスチャー部にHA(ハイドロキシアパタイト)をコーティングしたインプラントが登場しました。
HA は生体の成分と同様の成分を有し、骨形成において骨誘導能(バイオインテグレーション)が期待できるといわれました。HAではインプラント周囲1.5㎜まで骨ができるのに対し、チタンでは周囲0.3㎜が限界であるとの実験結果もあります。
日本でも1990年代に入りさまざまな製法が開発され、特に再結晶化HAをコーティングしたインプラントでは100%近い結晶度を実現。現在では早期のインテグレーションが得られるインプラントとして、広く臨床に応用されるようになっています。しかし、感染に弱いとの報告もあり、HAタイプが使用されているのは日本と韓国だけで欧米ではほとんど使用されていない状況です。
また1991年に表面が機械研磨(いわゆる削りだしの状態)より強酸で表面処理をした方が骨との結合がより強くなるという論文が発表され、それ以降各社表面をブラストや強酸により処理しラフサーフェス(微小粗雑構造)を作るようになり表面性状の良さを競っています。
現在さらに表面をフッ素コーティングをする事により骨伝導と石灰化が惹起され、治癒が早まると注目されています。日本ではまだ認可されていないが数年のうちに日本でもフッ素コーディングタイプのインプラントが登場する事が予想されています。このようなインプラントの改良により予後は日々向上しています。また適応も骨再生誘導療法などが開発され、歯槽骨の再生により拡大しています。2005年には、ジルコニアアバットメント(インプラント体と被せものをつなげる部分、通常は金属でつくられる)が日本国内で薬事法の認可を受け臨床応用が始まり審美的治療の幅も広がっています。